遺品整理のコツ|自分で行うメリット・準備するものや手順まで
- 2025年1月7日
- 読了時間: 10分
更新日:2025年1月24日

【目次】
遺品整理を自分でするには、気持ちの整理がつかないという人もいるかもしれません。
しかし業者に依頼する気にもなれないし、そのまま放置しておきたくはない…
遺品整理は時間も手間もかかる作業ですので、闇雲に始めてしまうと効率が悪くなってしまうかもしれません。
残された家族が遺品整理をする際に知っておきたいコツや具体的な手順、家族や親戚とのトラブルを回避するためには、どんな点に注意すればいいのかをまとめました。
遺品整理とは
遺品整理とは、亡くなった故人の遺品を整理することです。
業者に依頼した方がいいのかと迷う方もいるでしょうが、費用がかかってしまうというデメリットがあります。
残された遺族が遺品整理をする際のメリットや期限について、お伝えします。
遺品整理を家族が行うメリット
遺品整理の期限とは
遺品整理を家族が行うメリット

遺品整理を遺族が行うと、労力や時間がかかりますがメリットもあります。
業者に依頼すると気になるのが費用ですが、家族で遺品整理をすればもちろん費用はかかりません。
また思い出の品を見返す作業により、故人を偲ぶ時間を過ごせます。
ただし心の整理が済んでいないと、辛い時間になってしまうかもしれません。
遺品整理の期限とは
遺品整理には期限がある場合があります。
期限 | |
相続税の申請 | 10ヶ月以内 |
相続放棄の申請 | 3ヶ月 |
賃貸の退去期限 | 相続人が決める |
家の売却 | 引き渡し日まで |
故人が賃貸に1人暮らしをしていた場合は、相続人が賃貸借契約を引き継ぎます。
そのため家賃が払い続けられるようであれば、遺品整理を急ぐ必要はありません。
急ぐ必要はないとはいえ、無駄な家賃を払い続けるのは現実的ではありませんから、早く済ませてしまいたいというのが本音かもしれません。
家を売却する場合も、引き渡し日までは遺品整理の時間があると考えられます。
遺品整理はいつ始めてもいい
上記のような期限はありますが、基本的には遺品整理はいつ始めてもよいものです。
一般的には四十九日を終えてから遺品整理をする人が多いようです。
遺品整理は故人への気持ちの整理をつける行為となりますので、悲しみが癒えないうちは無理をしなくてもいいでしょう。
遺品整理をする前に
では残された家族が遺品整理をする前には、何を準備し、どのような計画をたてて取り組めばいいのでしょうか。
遺品整理を始める前に、これらの準備をしておきましょう。
遺言書やエンディングノートを確認する
捨ててはいけない物を把握する
家族と話し合っておく
人出を確保しておく
無理しすぎない
遺言書やエンディングノートを確認する
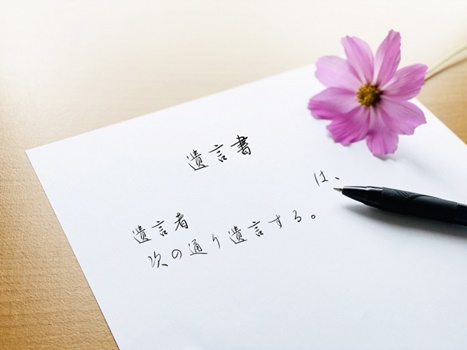
もし遺言書があれば法的効力のある書類となりますので、内容にしたがって相続を進めていかなければいけません。
エンディングノートに法的効力はありませんが、遺品整理や遺品分割について故人の希望が記されている場合もあります。
遺言書やエンディングノートの場所を聞かされていなければ、引き出しの中などまずは探す作業から始めてみましょう。
もし遺言書があったら、家庭裁判所で「検認」という手続きをした後に開封しないと法律違反となってしまいますので注意しましょう。
捨ててはいけない物を把握する
遺品整理をする際に物が多いと、手早く進めていきたいという気持ちが先立ち、捨ててはいけない物も捨ててしまうという失敗をしてしまうかもしれません。
金銭や相続に関するもの
身分証明書になるもの
返却しなければいけないもの
貴重品や貴金属
故人の形見となるもの
写真や手紙などの思い出
これらの物は、遺品整理で捨ててしまわないように注意しなければいけません。
場所がわかるのであれば、これらの物は先に別の場所に保管しておくと、誤って捨ててしまうという心配がありません。
書類系はまとめてチェック
遺品整理をしていると多くの書類が出てきますが、中には重要な書類もあるかもしれませんので中を確認しなければいけません。
年金や保険関連、不動産や公共料金に関する書類など、多くの種類があります。
遺品整理をしていく中で1枚1枚チェックしていると時間がかかりすぎてしまいますので、明らかに不要な書類以外は「書類」としてまとめておくようにしましょう。
「捨てていなければ何とかなる!」ものなので、書類は後で整理するようにシンプルに考えておくと作業がスムーズです。
家族と話し合っておく

遺品整理を始める前に、まずは家族揃って話し合いの場を設けるべきです。
「勝手に遺品整理を進められた」「大切な物を処分されてしまった」という親族間のトラブルに発展してしまう可能性があるからです。
遺品整理では誰が見ても不用品と判断できる物以外は、捨てないのがポイントです。
処分しようとしたら、生前故人に「譲ってもらう」という口約束をしていたというケースもあります。
「親族が集まるタイミングで現場を下見しておく」「遺品整理の役割を決めておく」というように、話し合っておくとトラブルを回避できます。
また認知症や突然亡くなってしまった場合には、遺産をどう分配するかも大事なテーマとなります。
人出を確保しておく
遺品整理を業者に依頼する場合は、田舎の旧家で4~6人、アパートの小さな部屋でも2人は必要となります。
細かな部分の整理であれば1人でも問題ありませんが、重い家具を動かす必要も出てきます。
また家族が遺品整理をする時には、長期スパンで行うというケースもあるでしょう。
「誰がいつ一緒に来てくれるのか」という人出の確保をしておくのがおすすめです。
無理しすぎない
遺品整理は故人との思い出がよみがえるので、辛い作業になるという方もいます。
故人はもういませんので、要不要の判断がつきにくく悩んでしまうかもしれません。
不要と判断できるものであっても、精神的に処分しにくいというケースもあり、遺品整理がなかなか進まなくなるかもしれません。
迷ったら家族に相談するなどして、1人で抱えこまないようにしましょう。
時間に余裕があれば遺品整理は急ぐ必要はありませんし、無理をせず業者に依頼をするという方法もあります。
遺品整理の手順とコツ
遺品整理を進めていく際には、以下のようなポイントを意識して行いましょう。
スケジュールを決めておく
作業に必要な道具をそろえる
必要な物と不用品を仕分ける
不用品を手放す
部屋の掃除をする
遺品を分配する
スケジュールを決めておく

「遺品整理をいつまでに終わらせるべきか」という時期を決めて、逆算していきましょう。
賃貸住宅の退去日というように期限があると、自ずとスケジュールが決まってくるでしょう。
なんとなく遺品整理をスタートすると、目途が立たずに効率の悪いものになってしまう危険があります。
まとめたゴミをすぐに出せるよう、粗大ごみの収集日やゴミ収集日を確認しておくといいでしょう。
作業に必要な道具をそろえる
遺品整理をスムーズに進めるためには、これらの道具を事前に用意しておくといいでしょう。
基本の道具 | ゴミ袋 段ボール ガムテープマジックペン |
あると役立つ道具 | カッターはさみペンチドライバー台車 |
安全対策のための道具 | 作業着軍手マスクスリッパ |
まず段ボールやゴミ袋は必須の道具であり、これらがないと遺品整理が始まりません。
家具の解体などや運び出しというシーンもありますので、カッターやドライバーもあるといいでしょう。
また遺品整理中には、ホコリが舞ってしまう、怪我をしてしまうという恐れもあります。
動きやすく、怪我をしにくい作業服を用意して、身を守るようにしましょう。
必要な物と不用品を仕分ける
スケジュールが木俣ら、遺品の仕分けをしていきます。
「残す物」「捨てる物」「保留」の3つに分けて、できるだけスピーディーに仕分けができるのが理想ですが、持ち主(故人)がいないため迷ってしまう場合もあるでしょう。
保留という項目を用意しておけば、すぐに処分を決断せずにすみます。
「一定期間保管したら」「家族に相談して」処分するかを決めていけばよいでしょう。
「今日はキッチン」「明日はリビング」というように、小スペースから始めていくといいでしょう。
最初に片付けた場所に、仕分けした遺品を整理していくと、仕分けした物が混ざってしまう心配がありません。
不用品を手放す
遺品整理で不要だと判断したものは、以下のような方法で処分していきます。
自治体のゴミ回収に出す
自治体のゴミ処理場への持ち込み
不用品回収業者に依頼する
知り合いに譲る
寄付をする
一般的な方法は、自治体のゴミ回収に出す、ゴミ処理場へ持ち込むという方法です。
一般ゴミで出せるものは問題ないですが、大きな家具や家電は不用品回収業者などプロに依頼した方がいいかもしれません。
遺品供養をしてもらう

故人の思い出の品を処分しにくいと感じる場合は、神社で遺品供養をしてもらうという方法もあります。
日本には昔から「物には魂が宿る」という考え方があり、物を手放す際には僧侶や神主に「魂抜き」としてお焚き上げをしてもらっていました。
現代では、写真や日記、ぬいぐるみ、眼鏡や杖などの愛用品を遺品供養する方が多いようです。
遺品供養をしてもらった方が気持ちがスッキリするという方は、検討してみてもいいでしょう。
部屋の掃除をする
部屋の荷物が片付いたら、掃除をしていきます。
賃貸住宅の場合は、原状回復をする必要があるため、入念な掃除が必要になると心得ておきましょう。
持ち家であっても、資産価値を維持していくために掃除は欠かせません。
ホコリが落ちるので、高い所から下に向かって掃除をしていくと、二度手間にならずスムーズに掃除ができます。
持ち家に誰も住まなくなった場合は、月に1~2回程度は風を通したり掃除ができると理想的です。
遺品を分配する
資産価値のある遺品を分配する際には、家族で揉めないように現金化するのがおすすめです。
金額が出せる遺品は、見積りや鑑定をしてもらうといいでしょう。
「形見としてほしい」という方もいるかもしれませんが、金額が明確になっていると後のトラブルを回避できます。
相続手続きの後に想定外の出費がかさむと、遺産分配に不満を感じるケースもあります。
遺品整理の不用品を売る

遺品整理で仕分けした物は、ゴミとして処分するだけでなく、買い取ってもらうという選択肢もあります。
リサイクルショップに持ち込み
ネットオークション・フリマアプリに出品
Pollet(ポレット)を利用する
リサイクルショップに持ち込み
リサイクルショップや質屋が近くにあれば、持ち込んで買い取ってもらうという方法があります。
しかしリサイクルショップや質屋は、「店舗によって値段にバラつきがある」「利益を出すために買取価格が安くなりがち」というデメリットがあります。
たくさんの荷物を持って何店舗も持ち込み、査定金額を比較するのは骨の折れる作業となるでしょう。
ネットオークション・フリマアプリに出品
ネットオークションやフリマアプリは、スマホが1台あればできるので手軽に出品できます。
しかしインターネットやスマホの操作に慣れていない年代の方だと、気後れしてしまうかもしれません。
手軽に使えるフリマアプリは、売れるまでどのくらいの時間がかかるかわからないというデメリットがあります。
「出品するために保管しておく」「売れるまで自宅に持ち帰る」というのは、現実的ではないかもしれません。
また「期待した値段で売れなかった」「送料が高くついた」「金銭トラブルに巻き込まれた」といったリスクがあると理解しておきましょう。
Pollet(ポレット)を利用する

リサイクルショップやフリマアプリよりも手軽な買取方法を探しているのであれば、Pollet(ポレット)がおすすめです。
Pollet(ポレット)であれば自宅で段ボールに詰めるだけなので、自身で持ち込む手間はありません。
また好きなタイミングで送ればいいので、すぐに不用品を手放せるといったメリットがあります。
買取カテゴリは60種類以上なので、意外な物が買取してもらえるかもしれません。
買取箱や送料、査定は全て無料です。
遺品整理はコツを掴んでスムーズに
遺品整理は業者に依頼してもいいですが、家族でも取り組める作業です。
故人の思い出話をしながら、家族とゆっくり取り組んでもいいでしょう。
どうしてもゴミや不用品の処理に悩まされてしまいますので、家族にとって負担の少ない方法を話し合っておくといいかもしれません。
Pollet(ポレット)の買取りをうまく活用し、スムーズに遺品整理を進めてください。


